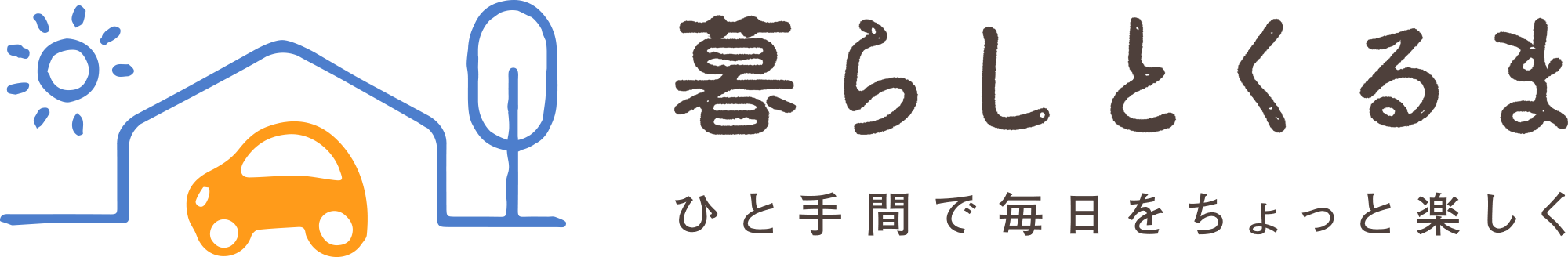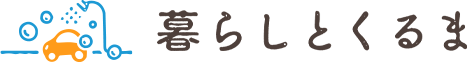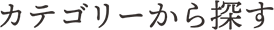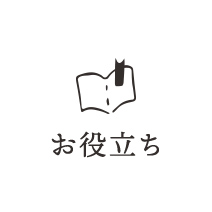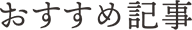運転席を見回したくなる!? よくわからないクルマのスイッチ3選
最新のクルマに乗ったとき、それまでのクルマにはなかったスイッチを見つけることはありませんか? 最新のクルマには、安全運転や快適なドライブをサポートする機能を使うスイッチが数多くあります。見たことない絵柄のスイッチだからと押すことをためらいがちですが、うまく使いこなせば、運転がラクになれるかもしれませんよ。
目次
最新のクルマに付いている、なんだか見たことのない絵柄のスイッチ
新車に買い替えたり、レンタカーなどで最新のクルマに乗ったときに、今まで見かけなかった絵柄のスイッチが付いていることはありませんか? 教習所などで教わった記憶もないし、押すと何が起きるかわからないので、そのままにしている方も多いかと思います。
実は、こういったもののほとんどは安全運転などをサポートする便利な機能のスイッチなんです。車種によって、機能の有無やスイッチの場所、表示サインが異なっているので、まずは取扱説明書を確認してみましょう。
これらのスイッチは実際に使ってみると、こんなに便利なのかと驚くこと間違いナシ! 思わず運転席周りを見直したくなる、そんな機能を3つご紹介しましょう。
信号待ちでブレーキを踏み続けなくてもいい「オートブレーキホールド」
まず1つ目は「オートブレーキホールド」スイッチ。
「BRAKE HOLD」「AUTO HOLD」「AVH」といったように、英語で書かれている場合が多く、たいていの場合は電子式サイドブレーキの近くに配置されています。スイッチを押すと、メーターパネルに機能が動作しているというランプ(または表示)がされることが多いです。

電子サイドブレーキの下に配置したオートブレーキホールドスイッチ(写真車種はHonda/FITクロスター仕様)
オートブレーキホールド機能は、クルマが完全に停止しているときにブレーキペダルから足を外しても、クルマが停車した状態を維持するというもの。
普通だと、オートマチック車の場合、クリープ現象でブレーキペダルから足を外したら緩やかに進みますが、この機能を使うと、ブレーキを踏み続けなくても停車状態を維持できます。
もちろん坂道でも使うことができます。解除はアクセルペダルを踏むだけと簡単。この機能を使えば、信号待ちのときにブレーキペダルを踏み続ける必要がなくなるばかりか、アクセルとブレーキを踏み変える回数が減りますので、足の疲労が大幅に軽減されます。都心部などで一度使うと手放せなくなるでしょう。
自動車付近の障害物を検知する「バックソナー(クリアランスソナー)」
つづいて、停車時や徐行時において、障害物を検知すると警告音を発する機能を搭載する車種に搭載するバックソナー(クリアランスソナー)スイッチ。ほとんどの場合、Pのマークと三角コーンの絵柄で表示され、運転席側ドアの近くの、やや押しずらい場所にあります。この位置にあるのは、基本的にはスイッチを「ON」の状態にしてほしい機能だからです。

ソナーのオン/オフスイッチ(写真車種はルノー/トゥインゴ EDCキャンパストップ仕様)
バックソナーは一般的に障害物から1.5mぐらいの距離から警告音が発生し始め、さらに障害物に近づいていくと、警告音の鳴る間隔が段階的に短くなり、最後は連続音になります。
これにより、駐車場の車止めなど、車両後方の下部の見えない部分にある障害物を運転手に知らせる便利な機能として役立てている方も多いかと思います。
-680x453.jpg)
車種によっては近くに障害物を検知すると、ナビ画面がソナー画面に切り替わるものもある(写真車種は日産/NISSAN GT-R NISMO)
でも、都心部などで信号待ちしているときに、自転車が近くに停止すると警告音を出し続けてしまい、運転に集中できないことも。そんなときにソナー機能を一時的にカットして、警告音を止めるのがこのスイッチです。
ほとんどは長押しすることで、オン/オフを切り替えます。頻繁に使うことはないかもしれませんが、どうしてもというときに使えるよう覚えておくといいかも知れません。
前走車との車間距離を保つ「アダプティブクルーズコントロール(ACC)」
最後はハンドルの右手親指部分に置かれている、クルマの下に横棒が並ぶ絵柄が描かれたボタンです。

ステアリングコラムの下部、青いスイッチの左側に設けられた車間設定スイッチ(写真車種は日産/スカイライン・ハイブリッド仕様)
これは「車間設定スイッチ」と呼ばれるもので、押すとメーターパネル上に絵柄と同じような画面が表示され、押すたびに横棒の本数が変わります。
-680x453.jpg)
メーターパネルの設定車速の左隣に設けられた車間表示
クルマによっては、運転者がセットした車速において、前走車との車間距離を保つように車間制御を行い走行するアダプティブクルーズコントロール(ACC)を搭載しています。このアダプティブクルーズコントロール使用時の車間距離を調整するのが、このスイッチです。※アダプティブクルーズコントロールの名称はメーカーによって異なります。
車間距離とその段階はメーカーによって異なり、さらに速度によっても異なります。例えば日産車の場合、時速100km/hのとき、”短”で約30メートル、”中”で約45メートル、”長”で約60メートルと3段階で車間距離の調整が可能です。さらに最近では車幅も監視し、車線中央付近を走行するようにハンドルを制御する運転支援機能と合わせた「同一車線自動運転(自動運転レベル2)」も実用化されています。
高速道路では、長時間にわたり巡行するため疲労が溜まりやすいです。これらの機能を正しく使えば、ドライバーの負担が軽くなり、安全性は大幅に向上しますね。

ここで紹介したスイッチは、自働車メーカーによって絵柄は若干異なりますが、ほぼ共通で使われているものです。スイッチを使う前には、取扱説明書などで機能をしっかり確認しましょう。それぞれの機能にもできないことがあるので過信しすぎは禁物です。その他にも、メーカー独自の機能もありますので、不明な点は取扱説明書で確認またはディーラーに尋ねてみてはいかがでしょう。
どの機能も安全運転や快適なドライブをサポートするもの。ぜひうまく活用して、毎日のカーライフをより豊かにしてみてはいかがでしょうか。
文・写真/栗原 祥光