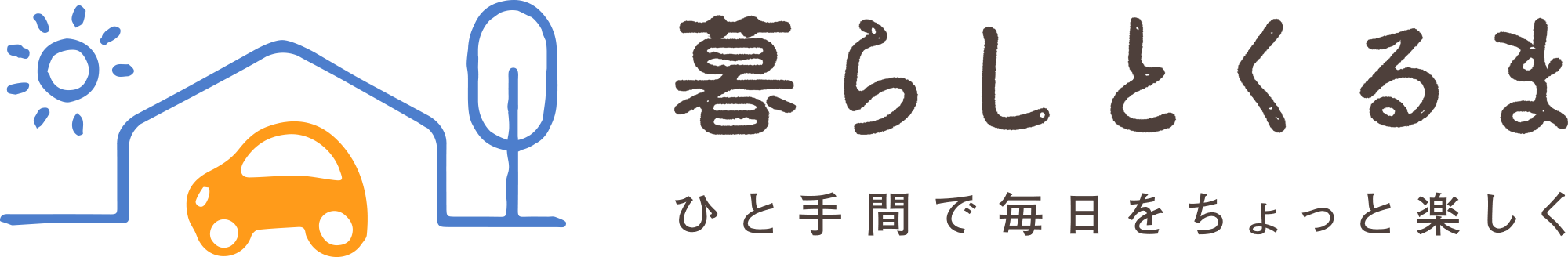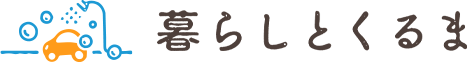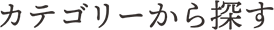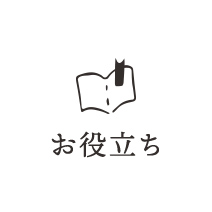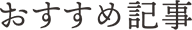大事な子どもの七五三。意外と抜けがち、着物での参拝で気をつけること
11月といえば七五三の季節。子どもの成長をお祝いする大切な行事ですよね。 そんな七五三では、着物を着た子どもたちの普段とは違った一面が見られ、お子さま自身はもちろん大人もドキドキしてしまいます。 同時に、違った意味でドキドキしてしまうのが、せっかくの着物が着崩れてしまわないかということ。お子さまも着慣れていないので扱い方が分かりません。クルマでの移動や参道を歩く際に大人がしっかりケアしてあげられるといいですね。
目次
近年のさまざまな七五三の形
最近は混雑を避けるため11月にこだわらず、早い時期から神社などに参拝される方も多くなっています。
また、「七五三は着物」というイメージが強いですが、記念写真(前撮りなど)は着物で、参拝は洋装というパターンもあります。着慣れない着物でご機嫌斜めになるくらいなら、ちょっとおしゃれな洋装でおめかしして笑顔でお参りできるほうがいいかもしれません。いずれにせよ、お子さまに合わせてあげるのが1番!

こちらでは着物を着て参拝するときのクルマでの移動時に気を付けたいポイントや、準備しておくといいものをお伝えします。
クルマの移動で気を付けたいこと
着付けは美容院や写真館などで行い、そこから参拝先までの移動ではクルマを使う方が多いのではないでしょうか。何も気にせずにクルマに乗せてしまうと、着崩れの原因になるので注意が必要です。少しのコツでそんな不安を解消することができます。
今回は3歳の女の子の和装を想定してお伝えします。5歳、7歳のお子さまにも応用できますので、ぜひ参考にしてみてください。

3歳の女の子は、帯を締めず、被布着(ひふぎ)と呼ばれるベストのようなものを着物の上に羽織ることが多いです
1. チャイルドシートへの乗せ方
6歳未満の子どもは、チャイルドシートもしくはジュニアシートの使用が必須です。これは着物のときも同様。
チャイルドシートは子どもの足の間にあるバックルに肩ベルトの金具を差し込んで固定しますが、この足を開かせるという動作が着物のときは難題。

着物を着たまま足を開くと、すぐに着崩れてしまいます……
チャイルドシートに座らせる前に着物の裾を折り上げておくと足の開閉がしやすくなりますよ。
【裾の折り上げ方】
① 着物の裾を持ち、② 優しく折り上げて ③ 腰ひもに裾(つま先辺り)を少しだけ挟む。折り上げすぎると着崩れの原因になってしまうので注意しましょう。
戻すときは、挟んでいた裾を直して軽く整えるだけ。強く引っぱるのは禁物です。

①褄先部分を持ちます(被布は脱いだ状態です)

②裾を優しく折り上げます

③折り上げた裾を腰紐に挟みます。もう片方も同様に折り上げて挟みましょう
また、お子さまの体型にもよりますが、ジュニアシートに切り替えるのも1つの手です。ジュニアシートはチャイルドシートと違い、通常のシートベルトを使って固定するので、足を開いてバックルに肩ベルトを固定する必要がありません。これを機にジュニアシートへのステップアップを検討してもいいかもしれませんね。
ジュニアシートの対象は身長135cm以下、体重15kg~36kgとなっていますので、お子さまの体型を確認してから使用してください。

ジュニアシートなら裾を折り上げなくても座らせることができます
2. ヘアセットを乱さないよう工夫を
着物と一緒に守りたいのがヘアセット。
きれいな髪形を崩さないためには座席に頭を付けないのがベストです。と言ってもなかなか難しいですよね。着付けで疲れて寝てしまったり、いつもの癖で頭を座席に付けてしまったり……そうならないためには、窓の外の景色を眺めるように促してみたり、お子さまの隣の席に座っておしゃべりをしてみたり、お子さまが横を向くことで座席に頭が付かない工夫をしてみましょう。
髪型にもよりますが、アップスタイルならバスタオルを丸めて首の後ろに挟んであげるのもいいかもしれません。

車内に常備しているブランケットを丸めて挟んであげました
3.クルマの乗り降りは頭上注意
乗降時はお子さまを抱っこすることもあると思いますが、ヘアセットによっては普段より頭(髪の毛)の高さが違うので頭上に注意しましょう。ささいなことですが大切なポイントです。
またお子さまによっては、自分で乗り降りする場合もあります。特に7歳になると自分で乗り降りすることが多いかもしれません。そのときにあると便利なのが低めの踏み台です。着物だと足を大きく広げられないので、低めの踏み台を使って階段のようにしてあげるとクルマの乗り降りがラクになりますよ。
おまけ:七五三のときに準備しておくといいもの
ここまではクルマ移動のときのポイントをお伝えしましたが、そのほか七五三のときに準備しておくといいものをご紹介します。
1. 履きなれた靴と靴下で歩きやすく

草履は履きなれていないので、いつも履いている靴や靴下を持っておくと安心です。写真撮影のときだけ草履で、歩くときは靴に履きかえるとお子さまもラクかと思います。草履しかなくてお子さまが歩いてくれず、終始抱っこのパターンも七五三ではあるあるです。
2. 大きめのタオルで汚れ防止
大切な着物を汚さないために大きめのタオルも持っておくと重宝します。エプロンのように前にかけて使えるよう後ろで留めるクリップ(洗濯ばさみ)があると心強いですよ。

3.飲み物はストローで飲めるものがおすすめ
女の子はメイクもするので口紅が落ちてしまうのを防ぐことができますし、コップやペットボトルだとこぼして着物を汚してしまう可能性も高くなります。
また、参拝後にそのまま食事会というパターンも多いですよね。食事会のときには着替えてしまってもいいかもしれません。着物の心配をするぐらいなら、着替えてストレスなく楽しい時間を過ごせるといいですね。
七五三は普段とは違い、慣れないことばかりで子どもも大人も気を張りがちですが、事前に予測しておけば心にゆとりができそうです。せっかくのお祝いの席。みんなが笑顔でお子さまの成長や健康をお祝いできるといいですね。