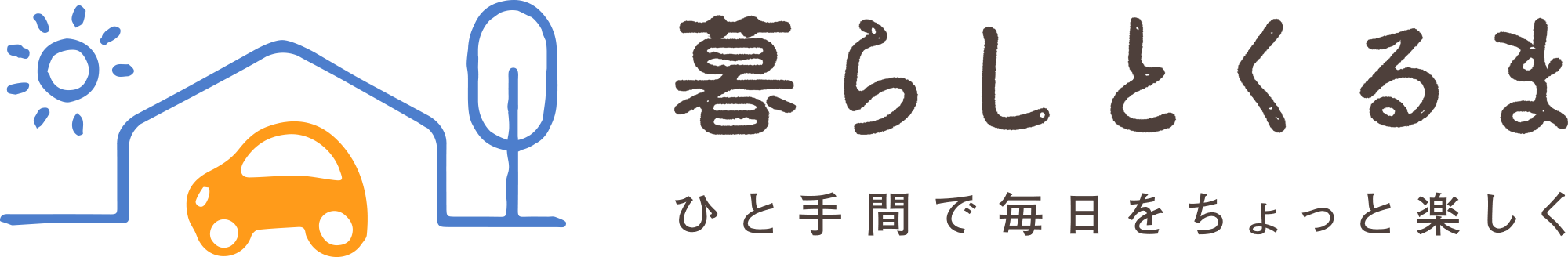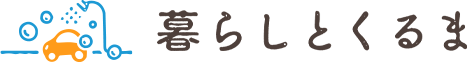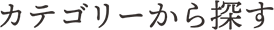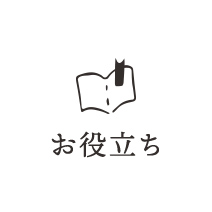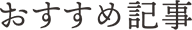意外と知らない! クルマの燃料「ハイオク」「レギュラー」「軽油」の違い
クルマを動かすのに必要な燃料を補給するガソリンスタンドには「ハイオク」「レギュラー」「軽油」の3種類の燃料があります。でも「軽自動車だから軽油?」という勘違いをしていたり、それぞれの燃料の違いについて実はよく知らなかったりしませんか? 今回は、そんなクルマの燃料について分かりやすくご紹介します。
目次
燃料の分類は、ガソリンと軽油の2種類
まずは、燃料の分類から見ていきましょう。クルマの燃料の種類は、大きく分けてガソリンと軽油の2種類があります。ガソリンには「ハイオク」と「レギュラー」が分類され、軽油はそのまま「軽油」が分類されます。どちらも原油からつくられていますが、沸点の違いによって分類されており、ガソリンは35〜180℃、軽油は240〜350℃となっています。
ガソリンと軽油の違い
ガソリン 軽油 沸点 35℃~180℃ 240℃~350℃ 引火点 -40℃以下 50℃~70℃ 着火点 300℃ 250℃
※引火点:火種を近づけた場合に燃え始める温度。着火点:火種のないところで自然に燃え始める温度
ハイオクガソリンとレギュラーガソリンの違い
それでは、ガソリンのハイオクとレギュラーは何が違うのでしょうか? これらは「オクタン価」という“異常燃焼の起こりにくさ”を示す数値が違います。
JIS規格(JIS K2202)では、ハイオクはオクタン価96以上、レギュラーはオクタン価89以上と定めています。つまりハイオクとは、ハイオクタン(high-octan、高オクタン価ガソリン)の名前のとおり、オクタン価の数値が高いガソリンを指しています。
ガソリン車のエンジンは、燃料と空気を圧縮して、点火プラグにより燃焼(小さな爆発)を起こしてエンジンを動かしています。オクタン価の高いガソリンの方が、この燃焼時の異常を起こしにくいため、高排気量車やスポーティーなクルマでは、オクタン価の高いハイオクガソリンがよく用いられます。
一方、レギュラーガソリンは、最も一般的な燃料であり、ハイオクと比べるとガソリン価格が1リットル当たり10円ほど安いという特徴があります。

軽油ってどんな燃料?
「軽油」は、ディーゼル(軽油)車の燃料です。軽油は、着火点がガソリンより低く、自然着火で燃料を燃焼させるためエンジンの構造がガソリン車とは異なります。また、高出力が出るので、バスやトラックなどのパワーが必要な大排気量の車両に向いている燃料です。
かつてディーゼル車は、空気を汚すイメージがあったかもしれませんが、最近では「クリーンディーゼル」と呼ばれる環境に配慮されたエンジンになっています。
軽油は、ガソリンよりも価格が安く、燃費も高い傾向にあります。しかし、ディーゼル車は車両価格が高いので、維持費は安くとも購入時には費用がかかることもあります。燃料によってクルマを選ぶときには、それぞれの特性を考えるといいかもしれません。
軽油って、軽自動車には入れられる?

これまでご説明した通り、ガソリンと軽油はまったく違うものなので、「“軽”油だから、軽自動車に入れられる」というのは間違いだとお分かりいただけるかと思います。
基本的に車種によって、ハイオク、レギュラー、軽油の燃料が指定されています。特にガソリンと軽油を間違えてしまうとエンジントラブルを招き、大がかりなメンテナンスが必要になります。また、同じガソリンでも、ハイオク指定の車両に、レギュラーガソリンを入れると車両の性能が十分発揮できないので、ご注意ください。
車種が指定する燃料を確認しましょう
車種ごとに、どんな種類の燃料を入れるかは決まっており、取扱説明書に記載されています。もし、シェアカーやレンタカーなどで「どの燃料を入れればいいんだっけ?」と悩んだときには、給油口にシールを貼ってあることも多いので確認してみましょう。給油口には、ハイオクなら「無鉛ハイオク」「無鉛プレミアム」、レギュラーなら「無鉛レギュラー」、軽油なら「軽油」「ディーゼル」などの記載があります。

また、ガソリンスタンドでは、ハイオクは黄色、レギュラーは赤色、軽油は緑でノズルの色が法令で指定されています。油種を間違えないようにノズルの色は統一されているので、マイカーをお持ちの方なら覚えておくといいですね。

燃料の違いを知って、安心して運転を
クルマに乗っていると燃料の補給は定期的に行うものです。それぞれの燃料の違いや特徴を知っておくと、クルマや運転に対する安心感がますのではないでしょうか? これからの運転が少しでも安心して楽しいものになりますように。